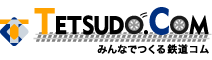2018年11月、東京メトロ千代田線6000系車両が約半世紀にも及ぶ活躍に終止符を打った。しかし、6000系の歴史はこれで終わったわけではない。大半の車両はインドネシアに渡り、新たな活躍の場を得ることとなった。
6000系のインドネシア通勤鉄道(KCI)への譲渡の歴史は2010年にさかのぼり、これまでに譲渡された総数は270両に達する。千代田線には最後まで6102編成と6130編成の2本が残っていたが、前者は当面の間東京メトロで保存されることとなり、2018年12月初旬、6130編成がインドネシアに旅立った。
これまで大々的にアナウンスされることのなかった6000系の海外譲渡であるが、新木場車両基地から搬出される6130編成の前後運転台窓には「The Last 6000 Series Tokyo Metro→Kereta Commuter Indonesia」という文言入りの特別装飾がなされた。
約3週間の船旅を経て、12月24日、あたかもクリスマスプレゼントのごとく6130編成がインドネシアに到着すると、早くも情報を聞きつけた多くの現地鉄道ファンたちが集まった。日本で盛大に鉄道ファンにお見送りされた車両であるが、当地でも鉄道ファンに出迎えられ、再びの人生ならぬ「車生」を歩み出したのだ。
「職人技」が必要な6000系
6000系は、当時の最新技術を引っ提げて1968年に一次試作車が登場した。当時は半導体技術の黎明期である。それゆえ編成ごとに搭載している機器のメーカーや機器自体に差異があるなど、保守整備には「職人技」を要する形式でもあった。
2010年~2013年にかけて、この「電機子チョッパ制御」の6000系がまずインドネシアに渡った。しかし、当時のKCIは手探り状態で日本の中古電車の運行を行っていた時代であり、さらに当時保有している車両のほとんどは半導体を用いない制御方式であったため、現場は6000系の扱いに手を焼いていた。
筆者と嶋村氏の出会いは2012年の暮れのこと。当時は6000系に不具合が多発しており、新たに日本から到着した車両すら営業運転できていなかった。筆者にも6000系の整備マニュアルが手に入らないかという依頼がKCIの車両担当者から入ることがあったが、そのようなものはなかった。
そんな中、突如KCIの車両担当者から電話があり、「東京メトロの方と話をしてもらいたいから至急来てくれ」と呼び出された。技術的な面に関しては門外漢、まして当時は片言だったインドネシア語で、果たしてそんな大役が務まるのかと、その時はヒヤヒヤした。
その際に判明したのは、空調制御器のマイコン部に取り付けられた電池の漏油による基盤の損傷であった。日本から来たばかりの運用開始前の車両に不具合が多発したのは、高温・多湿の環境下で機器の絶縁が低下しており、そんな中で車両の通電および各試験を行ったためであった。
運用開始後の故障調査にも大きな問題があったという。従来の車両は構内を走行させながら故障状況を確認し、その故障に関する機器の基盤をすべてチェックしていた。だが、この方法は電機子チョッパ制御車の場合、故障をより重症化させる恐れがあった。このようなことが、当時はまだ現場で知られていなかったのだ。
その名を知らぬ技術者はいない
その後の嶋村氏による地道な教育の結果、海を渡って日本からやってきた車両の現地での「立ち上げ」作業はマニュアルが作成され、KCIの作業者だけでできるまでにすっかり独り立ちした。車両故障の調査も簡易試験機を自作し、電子に特化した作業者が作成したマニュアルに従って故障を判断できるレベルにまで向上した。

KCIのカラーリングとなり、試運転を実施する6130編成(筆者撮影)
これらは、嶋村氏の半ば「草の根」的な活動の成果だ。この努力により、初期に譲渡された6000系13編成のうち11編成は、しっかりと整備が行われ、現在も活躍を続けている。
残念ながら機器故障から編成丸ごと廃車される車両も発生してはいるが、6000系を「教科書」として、KCIの電子技術が格段に向上したのは評価されるべきポイントである。
嶋村氏は1966年に当時の営団地下鉄に入団し、一貫して車両技術畑を歩んできた。6000系の登場はその2年後だ。「6000系は当時の最新技術を用いていることもあり、当初は故障などが頻繁に発生していた。毎日が勉強の日々で、メーカーと一緒になって作業をしながら技術を盗んでいた」と、嶋村氏は当時を振り返る。
「営団地下鉄は電機メーカーの壮大なる実験場であった」という嶋村氏。その車両技術開発の歴史は、日本の半導体技術の発展史でもあると力説する。1960年代末、6000系の制御装置に使用されていた半導体であるサイリスタは、80年代にはより小型のGTOに取って代わり、やがては現在主流の「IGBT」へと移り変わっていった。嶋村氏はこれらの進化を、営団地下鉄の技術者として第一線で見つめてきた。
一方、KCIには2007年、6000系の一世代前である東京メトロの5000系車両が譲渡され、2010年からは6000系が登場。さらに2016年以降は、IGBT素子を使用するインバーター制御に改造された6000系が渡ってきた。営団地下鉄・東京メトロで1960年代から2000年代にかけて進んだ技術革新を、KCIはわずか10年ちょっとの間に経験していることになる。
「次はいつ来てくれる?」
それらの車両を曲がりなりにも使いこなしているKCIの作業者は、嶋村氏にとっては愛弟子のような存在といえる。

KCIのスタッフに囲まれる嶋村氏(蛍光色のチョッキの男性)(写真:嶋村禎一)
現場で通訳を入れることはほとんどない。最低限の英語と身振り手振りのコミュニケーションになるが、専門用語を多用するために通訳を入れるとかえって通じないというのが嶋村氏のスタンスである。一歩現場に入れば怒号も辞さない「鬼」となるが、毎回帰国前にはレストランで作業者をねぎらうことも忘れない。そして「次はいつ来てもらえるのか?」との質問を作業者たちから浴びることになる。それこそが、嶋村氏の思いが確かに現場へ伝わっている証拠だ。
2015年のKCI入社時からデポック電車区で6000系のメンテナンスに関わっているユディ氏は、嶋村氏について「東京メトロの車両のすべてを知りつくしたエキスパート」と尊敬し、その人柄についても「若い技術者が大好きで、どんなことがあっても守ってくれる」「技術を分け隔てなく共有し、彼の知らないインドネシア特有の事象に対しては、真摯に学ぶ姿勢を持ってくれる」と賞賛する。
その言葉は、営団地下鉄時代から約40年、現場一筋で過ごしてきた嶋村氏の人となりをよく表しているといえるだろう。

6000系車内で作業中のKCIスタッフ(写真:嶋村禎一)
2014年以降、ジャカルタではJR東日本による技術支援も始まった。しかし、KCIは故障などの発生後に対処する「事後保全」的なメンテナンスを続けてきており、いきなり「予防保全」の検査方法を教育されてもどこまで対応できるのか疑問だと嶋村氏は言う。
単に教育するだけでなく、検査マニュアルがなぜ必要なのかを理解させるとともに、インドネシアの考え方を取り入れたうえで、その実情に合わせた新たなマニュアル作りをしてこそ本当の技術支援であると嶋村氏は提言する。実際に、KCIでは運行本数の拡充に伴う車両走行キロの増加により、整備の現場で新たな課題が発生している。このままだと事故につながる恐れもある。
また、嶋村氏は近年のビジネス的な支援の動きにも警鐘を鳴らす。純正品のスペアパーツを手に入れるルートが構築されたのは評価できるが、少なくともパーツを納入して終わりではなく、その後の指導もしなければならない。難しい部分ではあるが、国際貢献の意識を忘れてしまっては、安い中国製品に取って代わられる日が来るだろう。
人の心をつなぐ技術支援を
21世紀にも通用する車両として約50年前に開発された6000系は、東京メトロで大規模修繕を受けていることもあり、その設計思想のとおり今もなお古さを感じさせない。ただ、最近はチョッパ制御の6000系の故障が頻発しているのが気がかりである。

KCIのスタッフと嶋村氏(中央)(写真:嶋村禎一)
故障原因のほとんどは、GTO制御装置の経年劣化である。すでに日本で生産を中止している製品であり、廃車車両から取り外した予備部品でしのいでいるのが現状だ。ひとまず東京メトロからの車両譲渡は6130編成をもって終了することとなるが、単に車両を海外に譲渡するだけで満足せず、「Heart to heart」、人の心と心に響くような支援が継続されることを切に願う。
嶋村氏にとって、6000系は営団地下鉄への入団当初から世話をしてきたわが子のような存在。「できることは何でもお手伝いしたい」と語る。このような支援こそが、他国には絶対に真似のできない日本のものづくりの神髄ではなかろうか。50年を経ても陳腐化せず、6000系が遠く海を越えて走り続けられる秘訣がここにある。中古車両の輸出に限らず、日本の鉄道の海外戦略においても、大きなヒントになりえるのではないだろうか。